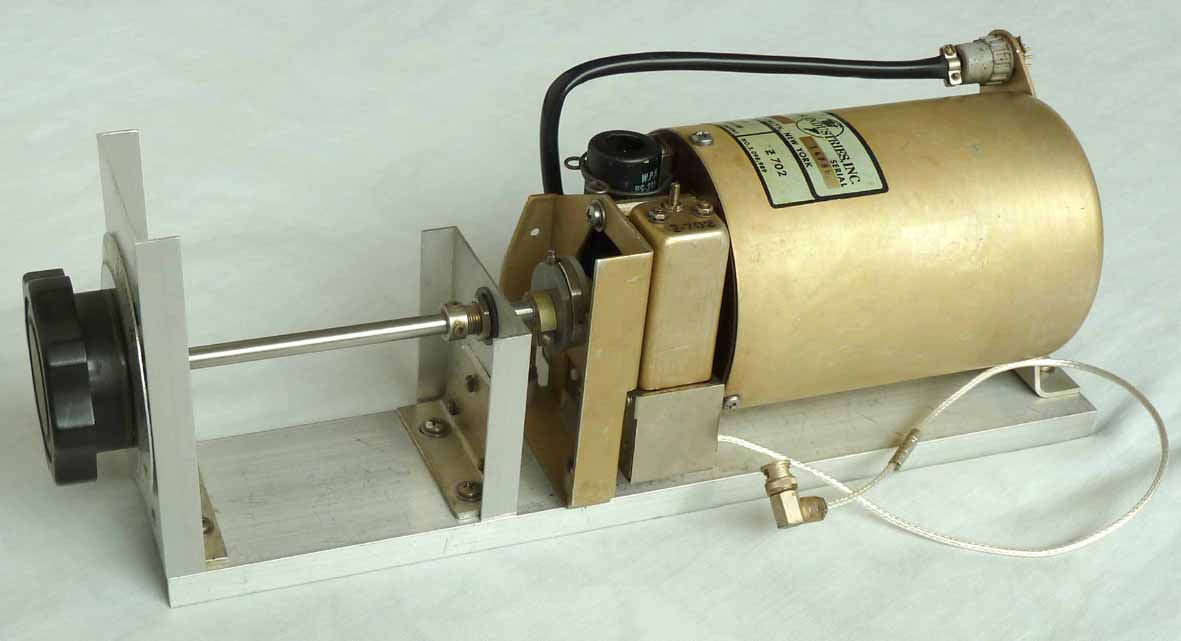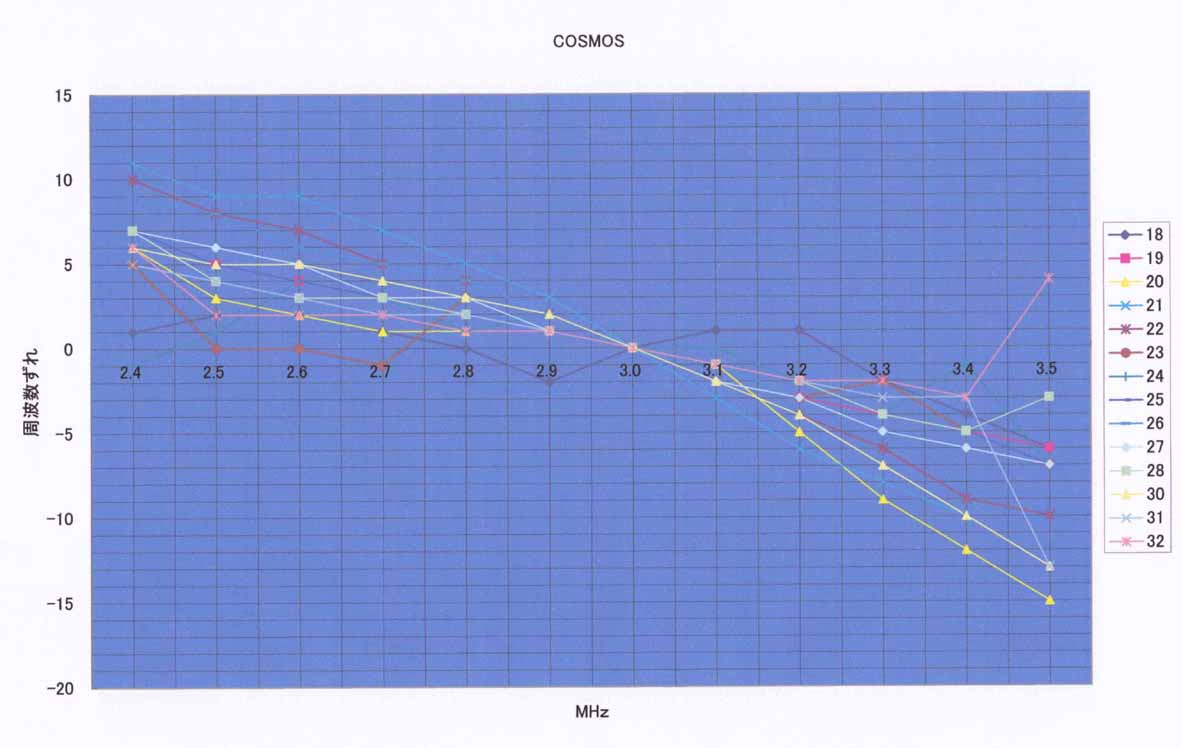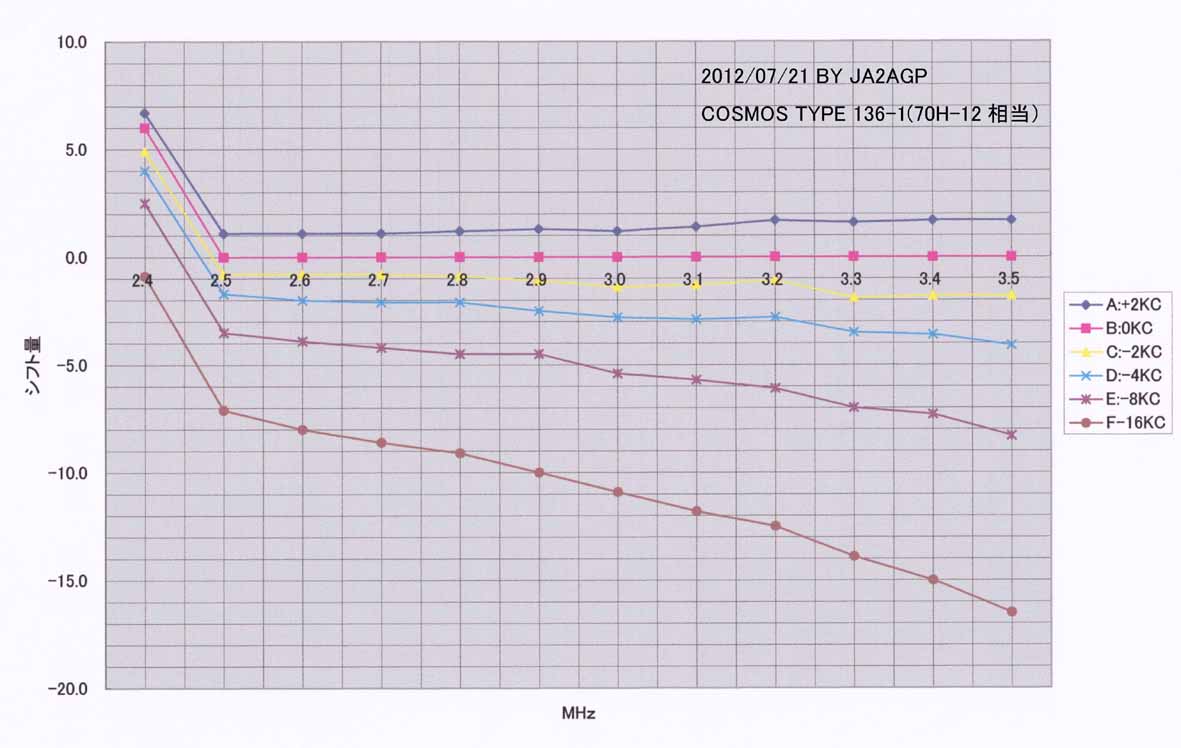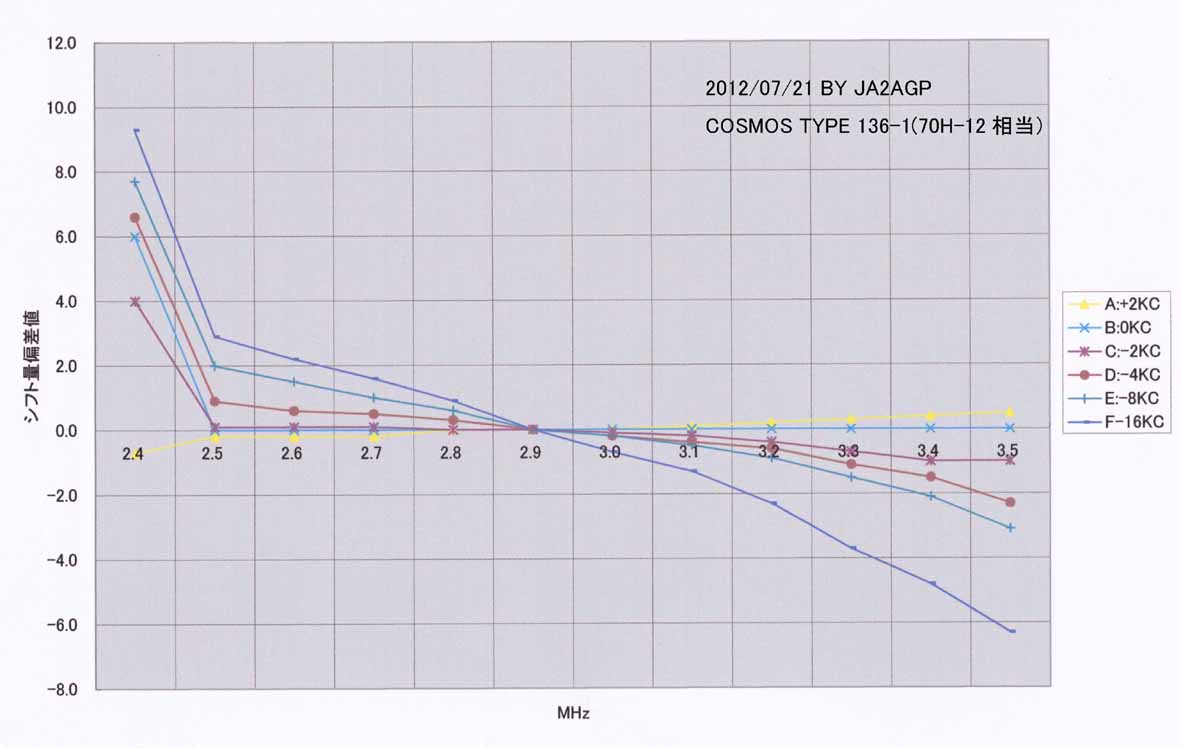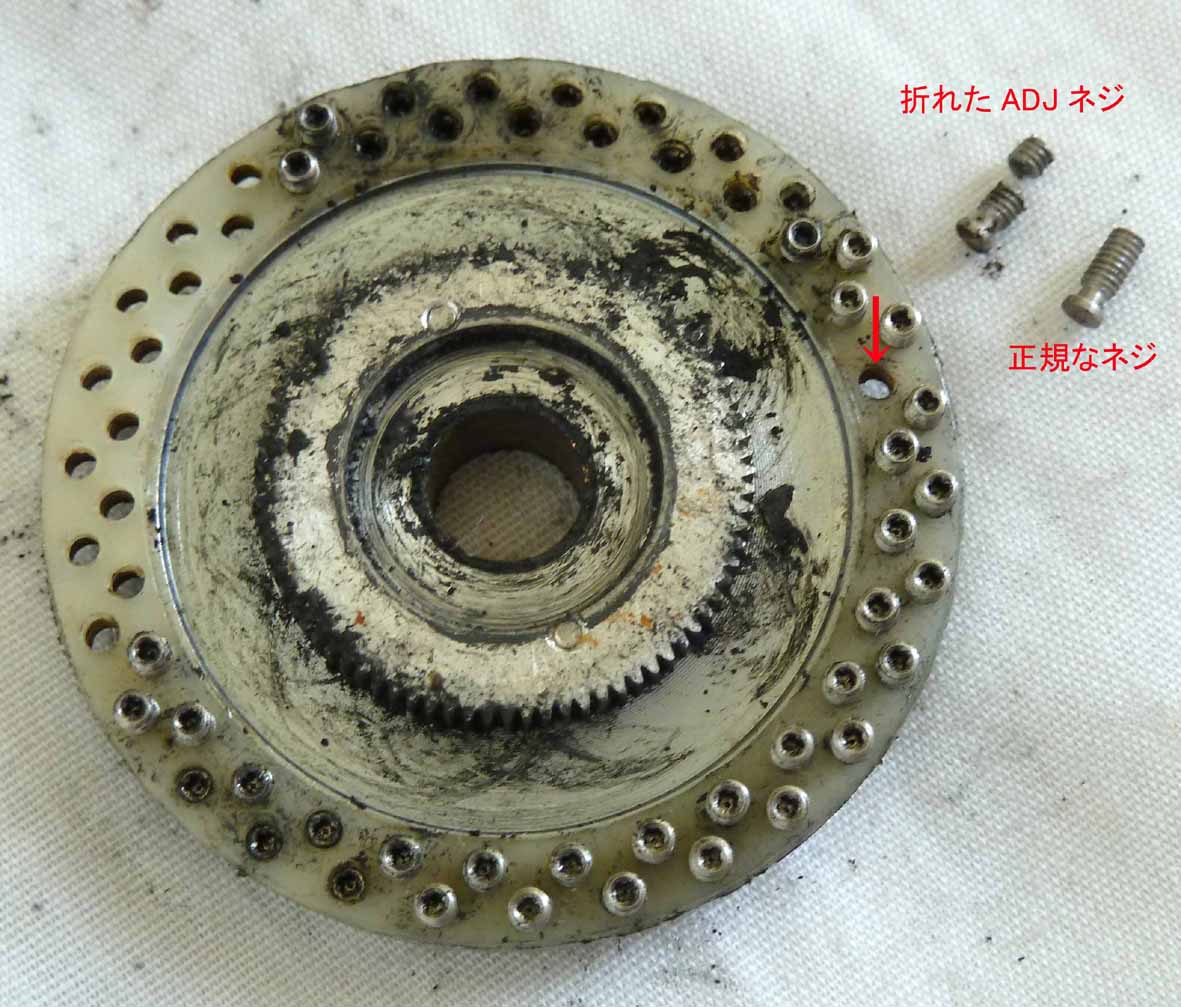COSMOS PTO TYPE 136-1(同等)調整要領
2012.07.21
JA2AGP 矢澤豊次郎 記
1.準備
(1)PTOシャフトに、100度目盛付き大型ツマミ(ダイヤル)を取付、1KCが読みとれる治具を作成する。
(2)治具は、PTOのリニアリティ調整コイルと補正スクリューを、ドライバーで調整可能な構造とする。
(3)PTOと治具の接続は、オルダムカプラとスプリングにより、バックラッシュのない構造で接続する。
(4)PTOの電源は、390A本体から延長ケーブルを作成して接続し供給する。(図1)
(5)PTORF出力端子に、周波数カウンターを接続する。

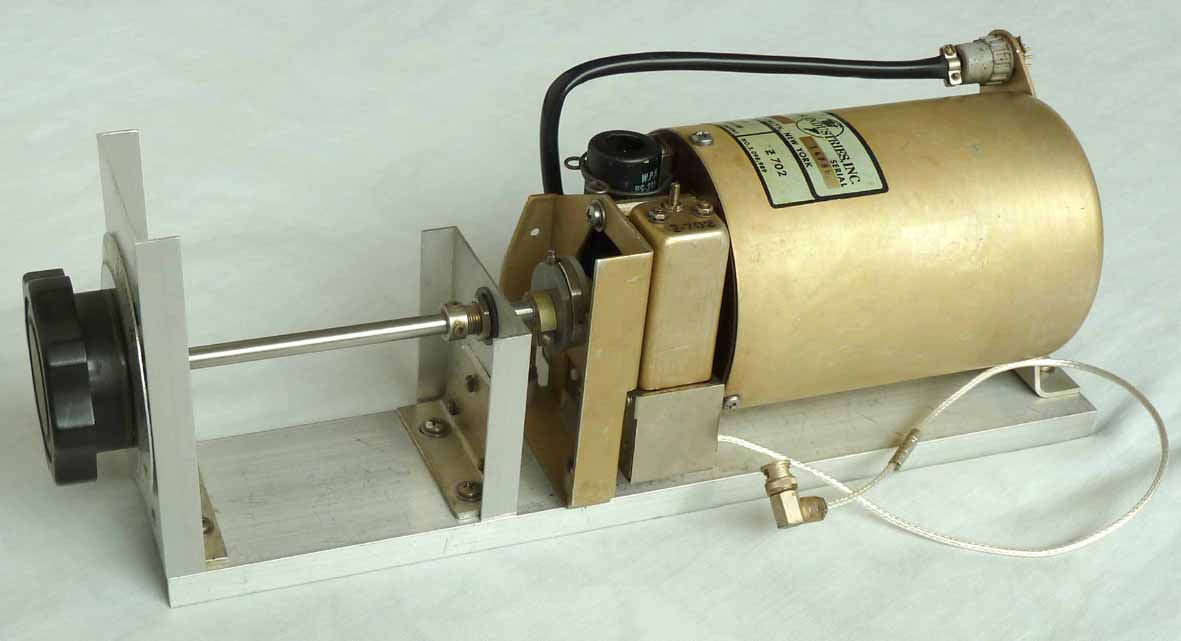
自作した治具 治具に136-1を実装した状態。電源とカウンターを接続し測定する。
2.事前確認
PTOのリニアリティの現状を確認する。
(1)PTOシャフトを回転させて、出力周波数が2955KCになるように合わせる。
(2)ダイヤル目盛を、55度に合わせてシャフトに固定する。
(3)ダイヤルを回転させて、ダイヤル目盛が0度毎に、周波数カウンターで周波数を読みとり記録する。
(2300KC〜3600KCの各100KC位置で、0.1KC単位で記録する)
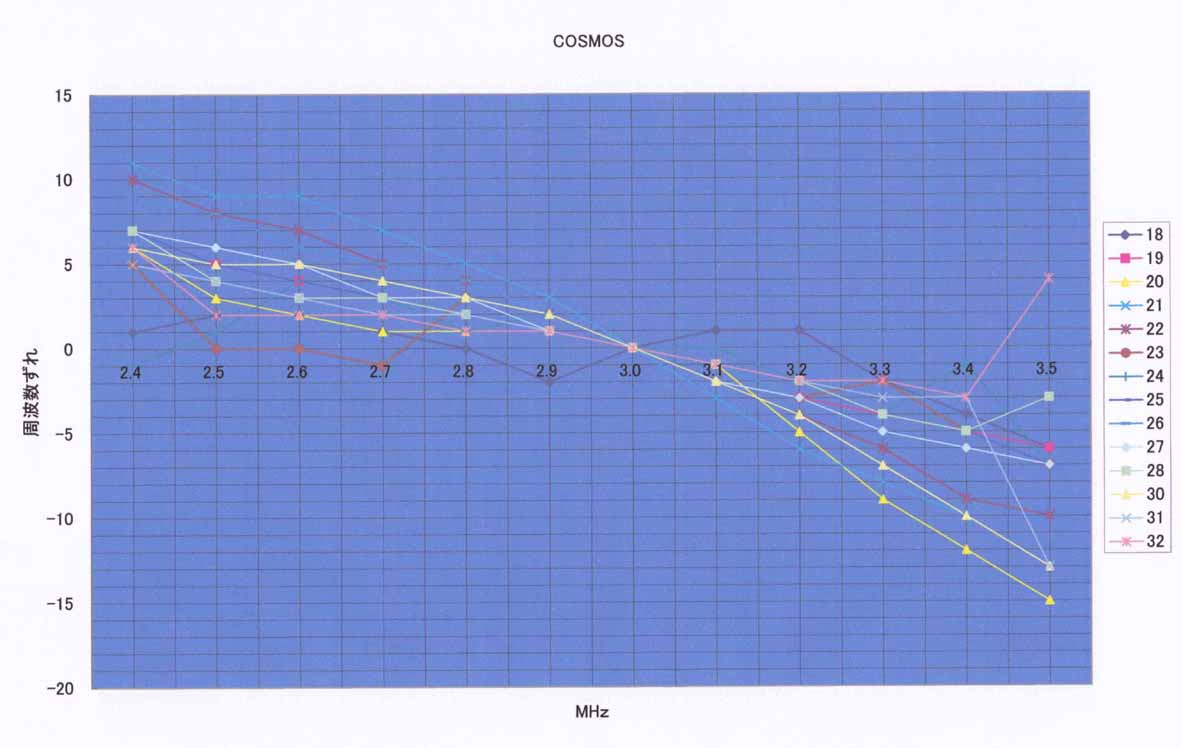
調整前に、発振周波数3.0MCを基準として、シャフト1回転毎にPTO発振周波数を測定すると
上図のように、2.4MCでは+5〜10KC、3.5MCでは-6〜15KCの周波数ずれが生じていた。
(サンプル数:COSMOS社製136-1 14台)
3.調整方法
STEP1:PTOシャフトの10回転と、周波数変化幅2455KC〜3455KCを一致させる。
(1)あらかじめ、リニアリティコイル調整孔と補正スクリュー調整孔の蓋ネジを取り外しておく。
(2)PTOシャフトを回転させて、出力周波数が2455KCになるように合わせる。
(3)ダイヤル目盛を、55度に合わせてシャフトに固定する。
(4)ダイヤルを回転させて、ダイヤル目盛が0度毎に、概ね100KC単位であることを確認しつつ、
3455KCまで変化させる。
(5)このとき、ダイヤルの目盛を、55度の位置で停止させて、周波数カウンターを読みとる。
(仕上がり状態では3455KCであるが、調整前では3455KC以下の状態が通例・・理由は後述)
(6)リニアリティ調整コイルのネジを廻して、カウンターの周波数が3455KCに調整する。
(リニアリティ調整コイルは、3455KCで±2KC変化させると、2455KCで±約1KCほど変化する。
この状況を表1に示す)
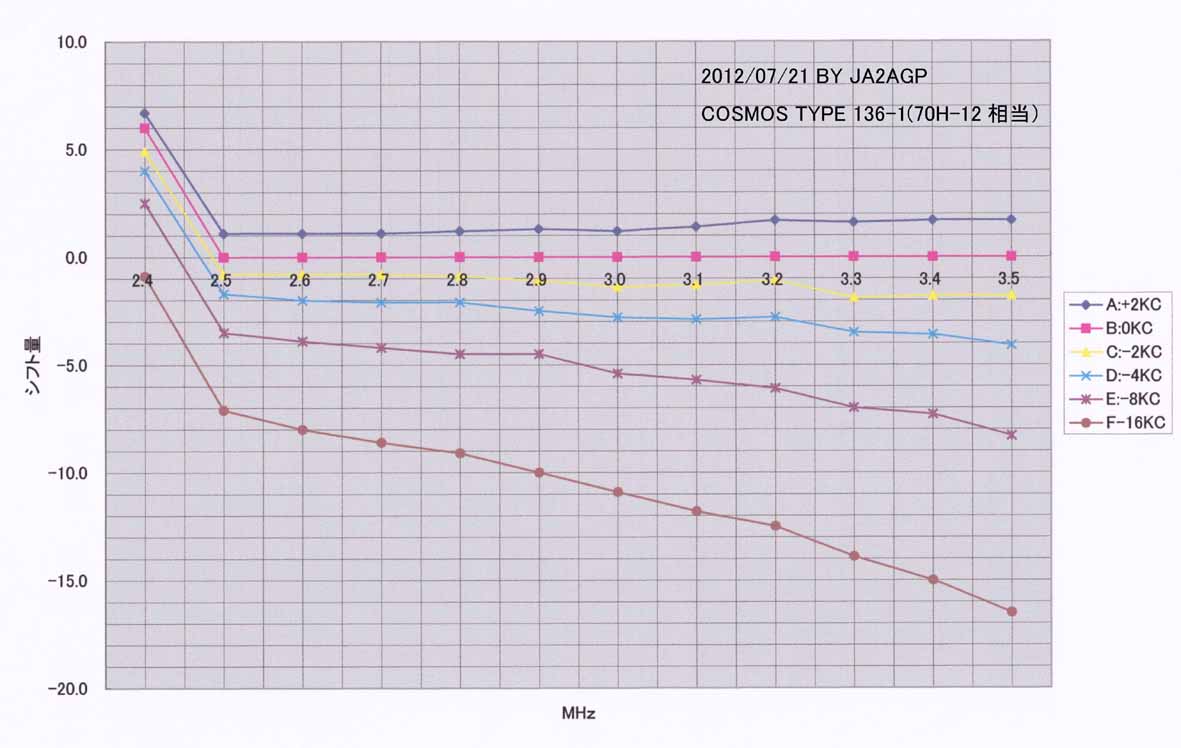
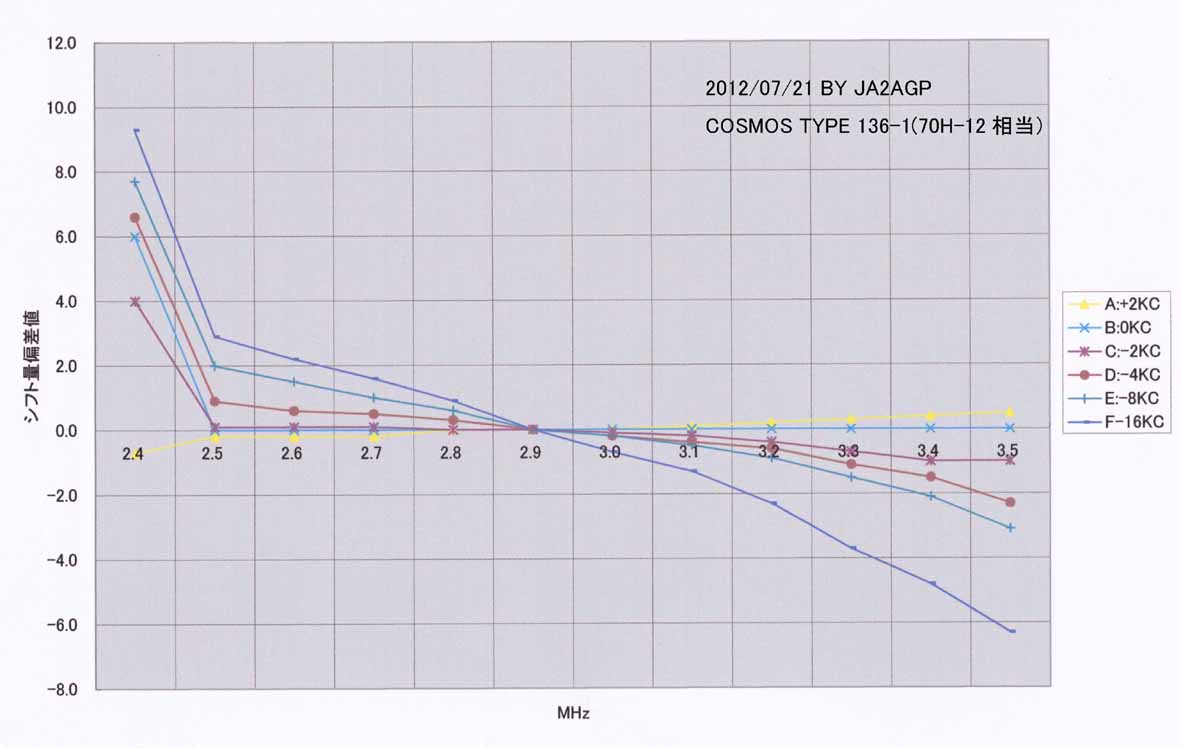
左図:リニアリティ調整コイル(EndPoint
ADJ Coil)を廻して、3.4MCで-2/+2/+4/+8/+16KC変化させると
2.5MCでは、およそ3.4MCの1/2の変化が生ずる。
右図:2.9MCを中心として置き換えると、リニアリティ調整コイルを調整することによって、2.9MCを中心
として、時計方向又は反時計方向に回転する形で、偏差を収斂させることが出来る。
その結果、シャフト1回転毎に100KCの変化が連続して、2.455と3.455KCにおいて概ねリニアリティが確保される。
(7)再び、ダイヤルを回転させて、出力周波数が2455KCになるように合わせる。
(8)出力周波数が2455KCのとき、ダイヤル目盛が55度となるように、ダイヤルを合わせ固定する。
(9)再び、ダイヤルを回転させて、3455KCまで変化させる。
この作業を繰り返して、PTOシャフトの10回転と、周波数変化幅2455KC〜3455KCを一致させる。
STEP2:次に25KC毎にPTOシャフトの1/4回転と、周波数変化幅25KC一致させる。
次の出力周波数とダイヤル目盛とが一致するように、補正スクリューを調整する。
(1)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2455KCのとき、ダイヤル目盛が55であることを確認する。
(2)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2500KCのとき、ダイヤル目盛が00であることを確認する。
(3)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2525KCのとき、ダイヤル目盛が25であることを確認する。
(4)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2555KCのとき、ダイヤル目盛が55であることを確認する。
(5)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2575KCのとき、ダイヤル目盛が75であることを確認する。
この調整を出力周波数2300KC〜3600KCで実施する
4.注意事項
(1)COSMOS PTOは、補正スクリューにより背面のスチールベルトを押し上げ、スチールベルトの
面で、ピストントリマーのシャフトを押し上げている。
このため、調整にあたっては、全ての補正スクリューがスチールベルトにタッチしている状態で調整
が完了しなければならない。
(2)この確認は、各25KCを調整する際に、隣接するスクリューを僅かに回転させて、周波数が変化する
ことを確認することが必要である。
(3)COSMOS PTOの補正スクリューは、製造時期によってマイナスネジ、スプラインネジのものがある。
5.雑感
(1)リニアリティコイル
リニアリティコイルの調整ネジが、封入ゴムで埋まっている状態で、明らかにメーカー出荷時の
ままであるが、リニアリティが外れているPTOがありました。(10回転で変化幅が1MC以下だった)
封入ゴムのかき出しは、先端を尖らせた特殊工具を作成して、遺跡の発掘紛いの作業で掘り出し。
リニアリティコイルの正規位置は、ネジしろのほぼ中央と思われますが、今回調整したほとんどの
PTOがネジしろが埋まった位置でTUNE完了でした。
このことから、PTO内部に実装されている同調用コンデンサーの経年変化が懸念されるので、取替
も考慮しましたが、温度係数等が未知数であること、同等品入手が困難であること、現状でなんとか
TUNE出来る範囲にあることなどから、コンデンサー取替は省略しました。
(2)補正スクリュー
補正スクリューのマイナスネジ頭の片山が飛んで、かまぼこ状態になっているものがかなりあります。
軍のメンテチームでは、リニアリティコイルの調整方法が解らずに、この状況を補正スクリューに
頼って補正しようとした様子ですが、補正しきれずにネジを廻しすぎて片山を飛ばしてしまい、
かまぼこ状態にした形跡があり、そのままの状態で終了したものと思われます。
その結果、正規調整をすれば「0.1KC以内の誤差」に入るのに、実測すると±5KCどころか
±10KCにもなるものが数多く存在し、スペック外れとなってしまっています。
(3)補正スクリューとスチールベルト1
補正スクリューの外円周側ネジを締め込むと、スチールベルトの外側車線を押し上げ、内円周側
1番ネジを締め込む。2番ネジを緩める。3番ネジを締め込む。この状態では、2番ネジはスチール
ベルトを支えない状態で浮いています。
この様な状態がないように、全てのネジが確実にスチールベルトを支える調整を行なう必要があり
ます。そのために、調整ネジの前後のネジが確実にスチールベルトを支えていることを確認するため
に、前後のネジを僅かに廻して、周波数が変化することを確認して下さい。


黒いリングのスチールベルトをフラット ネジ1本が25KC相当で、滑らかな傾斜状態
ヘッドがスライドして回転する が正常だが、段差が付いているのを注視。
(4)補正スクリューとスチールベルト2
補正スクリューのネジを締め込んで行くと、頭がベークライトの基台に埋まって回転しなくなります。
しかし、細いドライバーでさらに締め込んだり、キャップスクリューを力任せに締め込んだりすると、
さらに奥まで入り込んでしまいます。
この状態になると、スチールベルトが引っ掛かってしまって、PTOシャフトが回らなくなります。
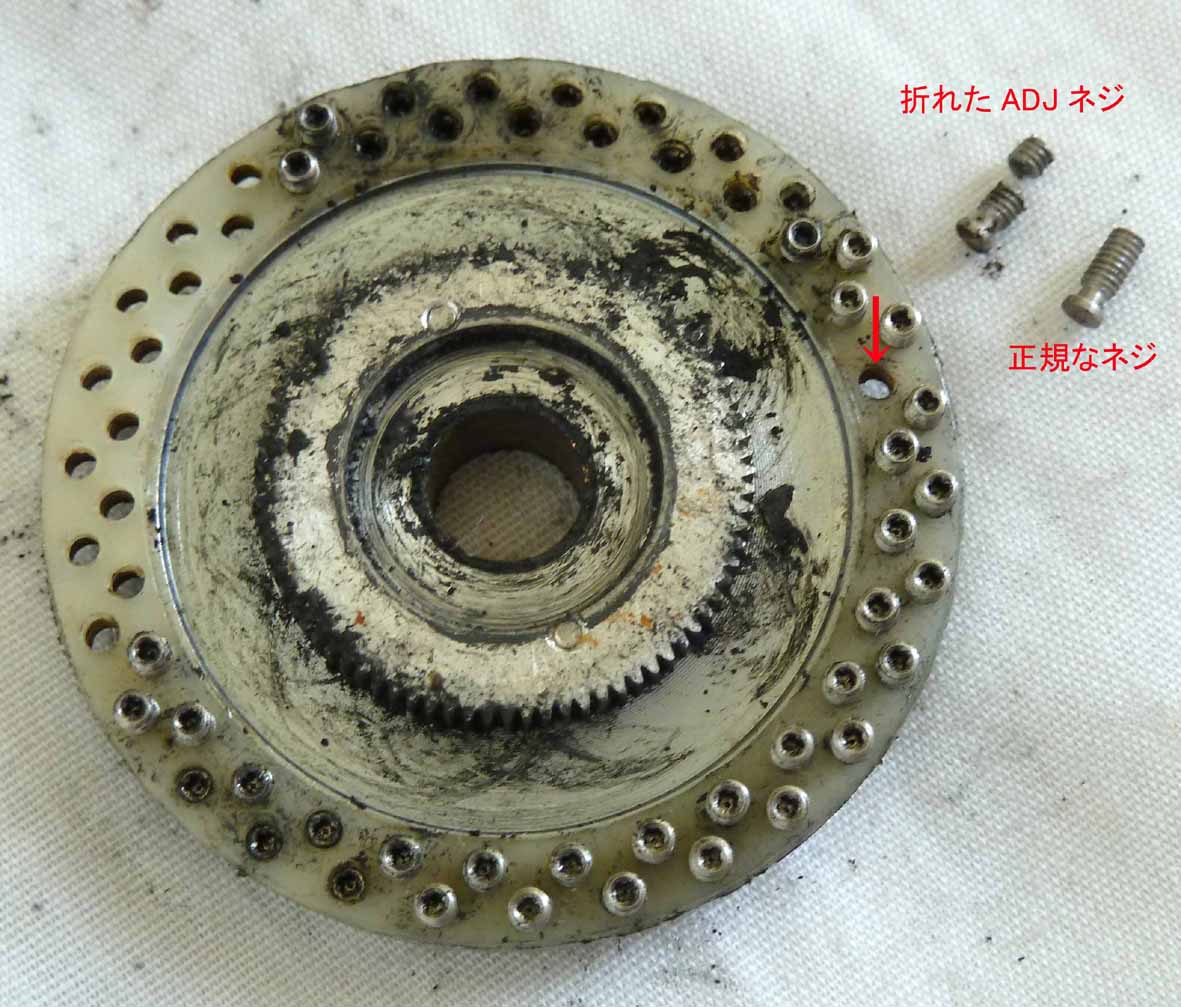

左下部分はかなり締めすぎ 締めすぎ部分が右下にあり大きく飛び出している
右上は折れたネジと、正常なネジを対比
補正スクリューの締めすぎには、くれぐれもご注意下さい。
R390Aメインテナンス 20へ
R390Aメインテナンス INDEXへ